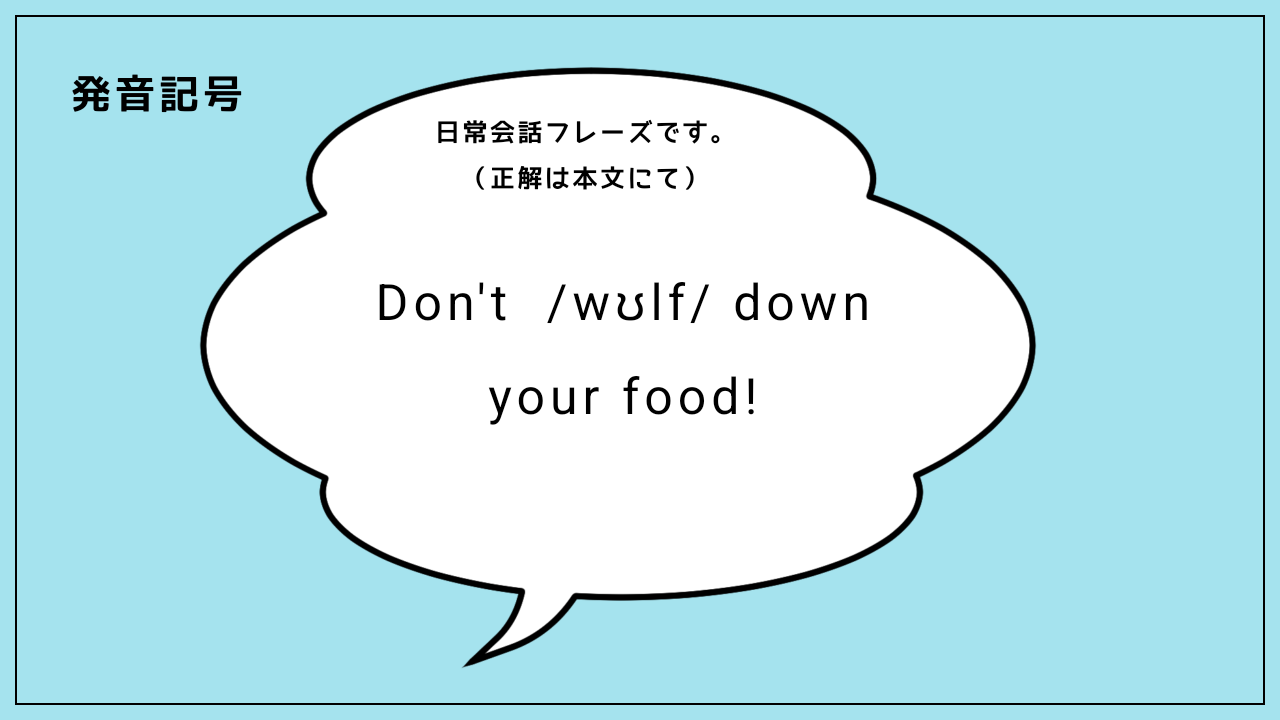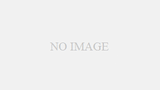こんにちは、中途失聴の英語学習者Ashley(アシュリー)です。
このブログの方針などはこちらをご覧ください。
今回は発音記号シリーズではなく文法面の解説です。
その前に。
私は中途失聴者なので、声を使うことは可能ですが、
声を使うことに苦痛はあります。
声を使うと、
「え?話せるの?じゃあ聞こえるんじゃないの?」と思い込む人が多く、
”聞こえないから分からない。筆談してほしい”
と訴えても理解してもらえず、
一方的に喋られた後で
「え?なんでこんなことが分からないの?」
という反応をされることが多いです。
そういうわけで、
個人的には「母語の声(日本語)を辞めたい」と常に思っています。
(家族の反対があり、家庭では声を継続中)
選べるものならば、
聞こえる世界を知った後に聴力を失うのではなく、
最初から「ろう」に生まれたかったです。
ただ、音声変換ツールを活用するにせよ、読唇で対応するにせよ、
声を辞めたとしても、
聴者の発音規則を理解する必要はあり、
さらに、日本語の場合は「読み仮名」というハードルから
声を使わない場合でもキーボード入力などで
聴者の発音(読み仮名)をアウトプットする力が求められます。
(英語の場合は綴りを覚えさえすればタイピングは問題ないですが)
さて。
中途失聴者の私の英語の発音は
完全失聴下で発音矯正を試みた結果、
一部の発音(R、T、Zなど)が
deaf voiceに近い発声になったようです。
※一般に中途失聴者の場合、
構音障害が進んだ人でも、ろう者とは違った発声であると言われますが、
外国語(特に母語に近い発音がないもの)を失聴後に視覚的・触覚的に習得しようとすると、
ろう者の声に近似していくのかもしれません。
私は自分のデフボイスを恥ずかしいとは思っていないし、
英語の方が、発音が聴覚に釣り合っているように思えてストレスがないです。
そういうわけで、今年6月受験予定の英検は
「フラッシュカード提示+口頭で答える」形式で申請しました。
(※英検は障がいなどに対する配慮申請が可能です。)
自分のデフボイスが試験でどの程度通じるのか楽しみです。
前置きが長くなりましたが、
今回は、日本語の概念にはない英語の時制「完了形」、
中でも「未来完了形」にフォーカスしてご紹介したいと思います。
例えば、
学校で生徒が先生に
“What time is our class over?”
“What time will our class end?”
と聞く場面があったとします。
この質問を日本語訳すると
どちらも「私たちのクラスは何時に終わりますか?」ですが、
ニュアンスに微妙な違いがあります。
現在形で聞いている
What time is our class over? の方は
「(終わり時間が決まっていることを)何時に終わるんだっけ?」
という確定事項の確認のニュアンス、
そして、
未来形で聞いている
“What time will our class end?の方は
「何時頃終わりますか」と、予測を含んだ聞き方をしています。
こういう聞き方をする時は、
「今日は親が早く迎えに来るって言ってたんだけどクラス何時に終わるかな」
「雨が酷すぎて電車止まるかも。帰れるかな。クラス何時に終わるんだろう」
というような、
何時までに帰れるか ”心配して聞いている” 時があります。
こういう時の返事としては
“We will finish by 5p.m.”
「17時に終わる予定です」
(予定を伝えるだけのニュアンス)
よりも
“We will have finished by 5p.m.”
「17時には確実に終わってるはずですよ」
のほうが、安心させるニュアンスを感じますよね。
こういう会話のように、
「確実に終わっているであろう」ことを言いたい時に
未来完了形が使われます。
〇未来完了形を例文で比較〇
「午後9時」を基準にした例:
・未来形
I will study English at 9 p.m.
→午後9時に勉強を始める予定。
・未来進行形
I will be studying English at 9 p.m.
→午後9時は勉強している途中。
・未来完了形
I will have studied English by 9 p.m.
→午後9時までには勉強が終わっている。
☆イメージとしては
時間経過を線上で考えて、
基準の時点(上記例文では午後9時)で
動作が「スタートする」のか、「進行中」なのか、
「既に終わっている」のか
で考えると分かりやすいかなと思います。